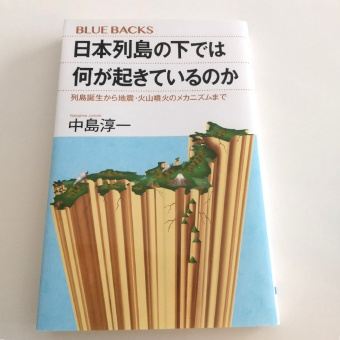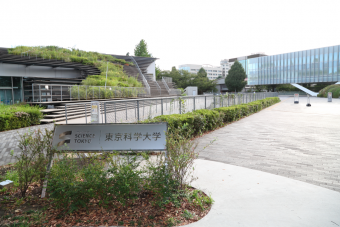博士の先達に聞く
困難な予知に挑み続ける地震研究の最前線と、博士たちの突破力を語る東京科学大学 中島教授。
-

-

近年、博士人材の産業界における価値やその活躍ぶりが喧伝されるケースが増えつつあります。実際に様々な企業の研究開発部門やコンサルティング部門が、工学系、情報系、薬学系等の人材を採用し活躍を促しています。そして理学系では数学や物理、化学といった分野の博士人材を高く評価し、優先的な採用に力を入れ始めています。では、それ以外の専門領域で研究に取り組む博士人材の、社会や産業界からの期待値はどれほど高いのでしょうか。
そこで今回は東京科学大学理学院の、地球惑星科学系教授である、中島淳一先生にお話をお伺いしました。中島先生は地震学の権威であり、大規模地震が起きた際にマスコミ各社から状況解説を求められる、国際的にも評価の高い有識者のひとりです。地震学は防災対策や災害予測の面で国家からも一般社会からも注目を集めている分野であり、 中島先生は国土地理院所管の地震予知連絡会の委員を務めるなど、社会との関わりが極めて深い活動をされています。中島先生には、地震学を専攻した博士人材の社会的な価値やキャリアの幅などについてお聞きするとともに、先生の世界的に注目されている研究内容についても語って頂きました。
(掲載開始日:2025年11月26日)
中島先生が長年取り組まれてきた研究内容をご紹介下さい。
地面を大きく揺らす地震の要因は、地球の表面層を覆うプレートと呼ばれる数十枚の巨大な岩盤層同士の衝突です。 プレートは、その下にあるマントルがゆっくりと対流することによって、年に数センチから10数センチほどの速さで動いています。しかし、プレートが地表近くを移動する方向はそれぞれ異なるので、その境界においてはプレート同士がぶつかったり、片方がもう一方の下に沈み込んだり、横にずれあったりします。その際にプレート境界やその内部には非常に大きな力が歪みとなって蓄積されるのですが、それが限界に到達して解放される時に巨大な振動である地震が生じるのです。
日本列島の周辺には北側に「北米プレート」、東側に「太平洋プレート」、さらにその南に「フィリピン海プレート」があり、西側には「ユーラシアプレート」が存在します。このように日本は複数のプレートに囲まれていることから、発生回数において世界的に突出している地震大国となっているのです。
地震学とは、こうした地震の発生メカニズムを研究し、最終的には正確な地震の発生予測に繋げることです。そのためには、まず地球の地下構造を解析し、どのような状態にあるのかを詳しく把握する必要があります。この直接見ることの出来ない地下構造の推定に使用されるのが地震波です。現在は、地震で生じた、地盤を伝わっていく振動(地震波)を全国各地に設置された千数百個の地震計が捉え、リアルタイムにデータ収集することで、以前に比べてかなり正確な地震観測が可能になっています。地盤を伝わる地震波は発生源から単純な同心円状に伝わるのではなく、水やマグマを多く含む地層では伝播が遅く、強固な岩盤層では速くなる特徴があります。その特徴を用いる事で、観測された地震波の到達時間の差や伝わり方(波形の形)をコンピュータ解析することにより、震源の位置や深さを特定するとともに、地下構造も朧げながらも推定できるようになってきました。
私は以上のような基礎的な地震研究に加えて、特殊な地下構造に由来する地震の発生メカニズムについても研究してきました。その一つの成果が、科学誌「Tectonophysics」に掲載された、海山の沈み込みによる地震発生メカニズムです。これは太平洋プレート上の海底の隆起した地形(海山)が、陸側のユーラシアプレートに沈み込む際に、その周辺に大きな地盤の歪みをもたらし地震を引き起こすとする考えです。この仮説を立てた私は、東京湾北部で頻発する地震活動に着目し、その地震活動の詳細な分布と関東地方沖合の太平洋プレート上にある海底地形の比較等を行い、東京湾北部の地震の巣は沈み込んだ海山が原因である可能性が高いと結論づけました。
現在、私が新たに取り組んでいるのが、山口県萩市の地下で突如始まった群発地震の発生原因の調査です。内陸部の深い場所での地震活動の原因を地震波データから突き止めようと試みています。
地震学を極めていくやりがいを教えて下さい。

地震学は理学の中で社会との関わりが特に強い学問です.防災・減災に向けては,地震学だけでなく地震工学や社会科学などとの連携も必要になります。
地震学の最終的な目的の一つが地震の正確な発生予測だと申しましたが、現時点では地震予知(時間・場所・規模を高い確度で事前に知ること)は不可能です。しばしば一般社会において気象学における天候予報と同列に扱われますが、予測に必要となる観測データ量には大きな隔たりがあります。例えば、台風や雨雲の動きは気象衛星の映像や観測レーダーなどにより可視化でき、またリアルタイムで気圧・風速等の膨大な観測データが集められるため、これら用いてシミュレーションや過去データとの照合により、精度の高い、信頼に足る予測を提示することが可能です。一方で、地震は直接見ることのできない地球内部の奥深くで発生しており、観測データも圧倒的に不足しています。そのため、地震の発生時刻や震源の場所を事前に正確に予測することは、空から地上に雷がいつどこに落ちるかを予測する以上に困難だと言えるでしょう。
それでも世間からの地震研究への期待値は極めて高いと感じています。それは、前兆現象を観測・解析し、高い確率で大規模地震の発生予知が可能になれば、それに対する事前の備えが充分にできるようになり、被害を最小限に抑えられるからであることは言うまでもありません。ひとたび大規模地震が発生すれば、地震学者はニュース解説などに呼ばれる他、マスコミ各社からは詳細な意見を求められ、次に起きる余震についての予測を聞かれます。
しかし、メディアなどで短期的な予測を求められるのに対して、現在の科学で可能なのは、長期的なターム且つ広範囲なエリアの確率論的な発生予測だけです。まだまだ世間から期待されている地震予知の精度からは大きくかけ離れています。今のところは、せいぜい30年内にマグニチュードX以上の地震が起きる確率はYY%である、といった範囲を推定できる程度です。その確度が急に向上することは当面ないでしょう。地震研究を進めていくに従って発生要因となり得る要素(パラメーター)は増えるばかりで、正確な予知は無理ではないかという考えに陥ることさえもあります。
それでも、観測データを一つ一つ丹念に拾い上げて分析し、様々な仮説検証を繰り返して地震という自然現象に関する知見を積み上げることで、地震対策への貢献は着実に生まれていくはずです。私は、たとえ地震研究からほんの少しの成果を得るのに膨大な時間と労力がかかっても、前進のために努力する意義は極めて大きいと感じています。
中島先生が地震研究を始められた発端と転機を教えて下さい。
私が生まれ育った茨城県南西部に位置する坂東市は、有感地震がとても多い地域で、地震に関しては幼い頃から身近なものと感じていました。また、母方の祖父が望遠鏡による天体観測が好きで、私もその影響を受けて宇宙に興味を持っていました。10歳の頃にハレー彗星が地球に接近したり、探査機ボイジャー1号と2号が木星や土星の鮮明な映像を地球に送ってきたりしたことも、当時の私が宇宙と地球について学びたいという思いに火をつけました。
高校入学後も宇宙や地球への興味は衰えず、大学を選ぶ際も東北大学の理学部物理系を受験しました。無事に合格はしたのですが、当初惹かれていた天文学のコースは狭き門であったことからもう一つの興味分野である地球物理学を専攻することになりました。これが地震学に向かうきっかけです。ただ、学部の頃はそれほど深い研究に携わることはなく、3年生の後期に地震学の研究室に入りましたが、基礎的な知識を習得することが中心で、地震研究が面白いと感じるには至っていませんでした。
転機が訪れたのは、修士1年になってからです。地震波に関する詳細な内容を自発的に調べたり、不明点を解読するアイデアを出したり、先輩たちから刺激を受けたりする中で、研究の面白さに目覚めました。地震研究者としての第一歩を踏み出した時期だと言えるでしょう。自ずと博士後期課程に進学する意思も固まりました。博士の学位を取得した後は日本学術振興会の特別研究員になったのですが、数ヶ月後に幸運にもポストが空き、東北大学大学院理学研究科の地震・噴火予知研究観測センターの助手に採用されました。アカデミアにおけるテニュアなキャリアのスタートです。
そして、その1年後に発生したのが、新潟県中越地震です。それまでは地震という自然現象を研究対象として捉えていましたが、この地震の直後に調査のために被災地に足を運んだところ、大規模な崖崩れや堰き止められた河川に大きなショックを覚え、避難所の方々と接することで大規模な自然災害という恐ろしさを目の当たりにしたのです。その時、地震研究者の一人として何かできることはないか、真剣に考えました。しかし、地震発生後に私にできることは限られており、ただただ自分の無力感に苛まれました。そこから、地震学を極めていくことで社会に貢献したいと強く意識するようになったのです。この想いは私の研究者人生における大きな原動力になっています。
研究者としても教育者としても大きな転機になったのは、2015年に東北大学大学院 理学研究科 地震・噴火予知研究観測センターの准教授から、東京工業大学(現東京科学大学)大学院 理工学研究科 地球惑星科学専攻の教授に移った時です。東北大学には全国から大量の地震データをリアルタイムで集める環境が整っており、それを処理する大型計算機も完備されていました。ところが東京工業大学ではそうした環境や計算資源がなく、研究環境をゼロから立ち上げ、データも自ら収集しなければなりませんでした。私はそれを残念に思うことなく、むしろポジティブに捉えました。大量のデータが揃わなくても可能な解析方法を考えるなど制約の中でも工夫を凝らし、研究手法そのものを見直したのです。この時の苦労で得た気づきは今の研究にかなり役立っています。
また、当時の東北大学の地震・噴火予知研究観測センターは学生が少なく、研究者(教員)たちがチームを組んで成果を目指すことが多かったのですが、東京工業大学に移ってからは毎年2〜3名の学生が研究室に入ってくるような環境になりました。私は学生たちの固定観念にとらわれない新鮮なアイデアや考え方から新たな気づきが得られることも多く、そうした学生たちを指導し共に学ぶ醍醐味も実感するようになり、教育者としての幅が広がったと思います。
地震学を専攻した博士人材にはどのようなキャリアがありますか。
私が東京工業大学に移ってから博士の学位を取得した3名の中島研究室出身者たちは皆、現在はアカデミアの研究者として活躍しています。また、修士で卒業した学生の中には気象庁に入庁したケースもあります。他にも、地震波を利用して地下構造を解析するスキルは、石油や天然ガスなどを探査する資源開発企業で活かされています。最近になって私は地熱発電の関連企業と共同研究を進める機会がありましたが、こうした分野や保険業内など少し変わった分野にも地震学を専攻した博士人材の進路が拓けていくのではないでしょうか。
地震学を学んだ博士人材への期待をお聞かせ下さい。
地震学は、産業界における研究開発業務とは大きく離れた学問領域に思われるかもしれません。でも、その過程で獲得する知識やスキルは、様々な企業で転用することが可能です。私は大学院時代の研究をアカデミアに進んで深化させることには大きな意義があると思いますが、一般企業に就職することによって自分の視野を広げ、自分の培ってきたスキルが思わぬところで発揮できる機会を得ることにも、大きな手応えを得られると考えています。
一方で、アカデミアの若手博士人材には、多くの先達研究者たちが様々な切り口で格闘し、微速ながら確実に地震学を前進させている中で、その成果を受け継ぎ、さらに中身を深化させていく役割を担っていただきたいと考えます。私のようなベテラン研究員たちが残してきた成果を土台に、さらに新しい知見を積み重ねていってほしいのです。まだまだ解き明かすべき謎の多い地震学には、そのような若手の博士人材が欠かせないのです。
博士・ポスドクへの応援メッセージをお願いします。
博士人材は自分で研究テーマという入口を決め、論文という出口を見据えて、自らをマネジメントする経験を持っています。特に、自ら決めた研究テーマが暗礁に乗り上げた時、それでも突っ込むか、別のテーマにスイッチするか、それを模索しながら方向性を自分で決め、最終的に乗り越えた博士人材には、高い壁を突破する力が備わっているはずです。博士という学位の取得に大きな意義を感じて、産業界でもアカデミアでも、ご自身の選択した世界で大いにご活躍下さい。