博士の先達に聞く
指導教授として数多くの博士を輩出してきた、 東京科学大学 熊井教授が語る博士人材の価値。
-

-

東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により、2024年に設立された東京科学大学。過去5年間の掲載論文数と被引用回数に基づいて算出される「h-5指標」では、東京大学に次ぐ日本第2位の研究機関です。そうした多大な研究実績とリンクして、同大学は研究者の育成面でも定評があります。アカデミアはもちろん、産業界の最先端で活躍する研究者の中においても、同大学出身の博士はメジャーな存在となっています。
そんな東京科学大学において、世界的に注視される研究を続けられる一方で、研究室主催者(PI)の立場で多くの大学院生を指導し、数多くの博士を世に送り出してこられたのが、熊井真次教授です。金属工学が専門の熊井先生は、特にアルミニウムの研究に関して世界的な権威であり、学術的基礎と工学的応用の両面で多くの研究成果を挙げられています。実際にそうした熊井先生の研究成果は高く評価されており、現在までに軽金属学会や日本金属学会、軽金属溶接協会、日本鋳造工学会などから多数の表彰を受け、2012年からはICAA(アルミニウム合金国際会議:The International Conference on Aluminium Alloys)においては国際委員を務めていらっしゃいます。
そこで熊井先生に、アルミニウムに関する多様な研究をどのような姿勢で推進してきたのか、そして、その中で博士人材は熊井先生のどのような研究スキルを伝授されて第一線に巣立っていったのかを語って頂きました。熊井先生のお人柄が伝わってくるインタビューでした。
(掲載開始日:2025年7月28日)
熊井先生が現在取り組まれているアルミニウムに関する研究内容をご紹介下さい。

退職時のメッセージに「金属50年」と言葉に象徴される金属材料、特にアルミニウムの探求に情熱を注がれました。写真は、液体アルミニウムが冷える過程で、固相(結晶)が形成され、最初の結晶が、樹枝状に成長した、アルミニウムのデンドライト(樹枝状晶)。この大きさは非常に珍しいという事です。
私はアルミニウムという材料について複数のテーマを変遷しながら研究成果を積み重ね、その過程で様々なアルミニウム合金の特性やそれらの製造技術に関する知見を高めてきました。そして、現在は2つのテーマに取り組んでいます。
一つはアルミニウムのリサイクル技術です。アルミニウムは原料であるボーキサイトからアルミナという中間物に変換し、それを電解精錬してアルミニウムを得る際に、大量の電力を使用します。軽くて強く、錆びないという特性を持ったアルミニウム合金は持続可能な社会を目指す現代において高い価値を持つ一方で、電解精錬時にCO2を排出するという問題を抱えているのです。
そこで以前から普及していたのが、アルミニウムスクラップを溶かして「再生地金」にするリサイクル技術です。この方法では、ボーキサイトから「新地金」を製造した場合に比べ、CO2排出はわずか5%以下に抑えられます。しかし現在のリサイクル技術では、再生地金に不純物が残ってしまい、低品質である鋳造材への用途に限られます。純度の高いことから強度や成形性に優れる高品質の「展伸材」※は、今のところ新地金から圧延や押出などの工程を経てからしか造ることができません。そこで、私は再生地金を展伸材へと導くリサイクル技術の確立に挑んでいるのです。この目的で新しく開発しているリサイクル技術が「縦型高速双ロール鋳造」という加工製造技術です。この製造法を確立できれば、低品質な再生地金から高品質の展伸材を産み出すアップグレードリサイクルが可能になり、カーボンフリー社会の実現に大きく寄与出来ると考えています。そしてこの研究はNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の実用化研究である「資源循環型社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発」に採択されました。アルミニウムユーザー企業のトヨタ自動車や本田技研工業、デンソー、東洋製罐などの企業も参加する国家プロジェクトとなっているのです。
もう一つのテーマは、異なる金属材料同士を接合する接合技術の開発です。自動車をはじめとする現在の工業製品の多くは、異なる材料を接合して仕上げるマルチマテリアル化が進んでいます。ただ、今までの溶接等では接合部の強度低下や劣化に問題がありました。そこで私は、爆発圧接や電磁圧接といった高速衝突を利用した固相接合法に注目。マイクロ秒の極めて短時間で発生する「メタルジェット」(衝突時に金属が噴き出す現象)や界面の波状パターン形成メカニズムをシミュレーション等で解析することにより、異種金属接合部の組織を制御することに成功しています。この成果は、自動車や鉄道、航空宇宙など、高強度軽量構造物を必要とする幅広い分野を前進させると期待されています。
※展伸材:金属材料を圧延、鍛造、引抜き、押し出しなどの加工方法で、板、条、棒、線、管、形材などの形状にした材料のことで、これらの材料は、強度や耐久性が高く、建築、自動車部品、家具、電気機器など、幅広い分野で使用されています。
熊井先生はどのような研究キャリアを歩んでこられたのでしょうか。

東京工業大学(現:東京科学大学)へ久留米高専から編入学し、博士課程修了後も大学に残りましたが、そこでは、学生時代の研究テーマを継続することが出来ませんでした。
それでもチャレンジは必ずプラスになると考え、新たな研究に取り組んだことが後に大きな財産となる海外留学に繋がりました。
私は、東京工業大学には久留米工業高等専門学校(以下高専)の金属工学科からの編入で学部3年生から入学しました。ですから高専の卒業時には金属工学に関する基礎知識を身につけており、学部でさらに金属工学の知見を深めました。アルミニウムを専門とすることになったのは、学部の卒業研究に向けて非鉄金属の研究室に入ったのがきっかけです。この研究室を選んだのは、先生方が人間的にも非常に魅力的であったことも大きいのですが、金属工学の本流とされる鉄鋼ではなく、アルミニウムの分野に貢献したい気持ちがあったからです。その頃はチタンやマグネシウムが非鉄金属研究で注目され始め、アルミニウムを専門としていた研究者が少なくなってきていましたが、古くからの素材であったアルミニウムの研究開発はまだまだ社会が必要としていると、私は考えました。
その後、修士課程を経て博士課程に進学し、アルミニウムの研究を継続していました。当時、博士の学位を取得してからも大学に残って研究を続けたいという意思があったのですが、文部省の人員削減が噂され、東京工業大学のメインキャンパスである大岡山の研究者ポストは空かないと言われていました。そんな博士課程3年(D3)の時、横浜市にある、すずかけ台キャンパスの精密工学研究所から助手の声がかかったのです。今までの博士課程で行っていた研究テーマを継続することはできませんが、それでも私は新たなチャレンジは流れの中でベストの選択であると考えました。実際、この精密工学研究所の気風が海外留学を重視していたことにより、1987年の30歳時に、日本学術振興会の海外特別研究員制度を活用して英国のケンブリッジ大学で2年間にわたって留学し、客員研究員を務めることになりました。
アルミニウム研究の最前線を歩まれた中でご苦労された経験はありますか。
私の金属工学の研究者キャリアは壁の連続です。まず、高専の入学が本意ではありませんでした。事実、中学生時代の好きな科目、得意な科目は国語と英語でした。ところが当時の実家が営んでいた事業が芳しくなかったことから、授業料や寮費が格安だった国立高専への進学を決めたのです。金属工学科を選んだのも、入試の倍率が最も低かったからです。それでも私は金属工学を好きになろうと考えました。
そして最初は英語の先生、その後に多くの金属工学の先生から熱い指導を受け、学ぶことの楽しさ、壁を乗り越えることでの成長感を知ることになったのです。英語のご指導のお陰で高専時代には朝日新聞が主催する全日本高等学校英語弁論大会で3位に入賞しています。また、東京工業大学への編入学試験の準備においても、応援してくれる入試科目の各先生方からマンツーマンによる講習を受けています。
ケンブリッジ大学の留学から帰国した後にも、キャリアの面で大きな壁が立ち塞がりました。ケンブリッジ大学で得た研究方法や英国の研究者と築いた太いパイプの存在が仇となって、従来の研究スタイルを進める研究室とのミスマッチを感じるようになったのです。このまま研究室に残ると助手から昇進できない懸念から、毎日求人誌を見る日々が続いたのです。そうした中で心強かったのが、私を応援してくれる人が少なくなかったことです。ケンブリッジ大学において金属工学の世界的権威であり上司でもあったジョン・ノット先生は、私にアルミ複合材料など新たなテーマを追いかける意義や醍醐味を教えてくれましたし、一緒に研究したジュリア・キング先生とは帰国後も文通を続け、研究環境に関する悩みを打ち明けると「英国の研究職を紹介するわよ」などと励ましてくれたのです。ちなみにキング先生は後にアストン大学の副学長になり、バロネス(女性男爵)の爵位を授与されています。
そして、日本においても東京工業大学の金属工学研究をリードする加藤雅治先生と三島良直先生が私の研究内容を高くご評価頂き、大岡山キャンパスの助教授昇進をアシストしてくれたのです。加藤先生の、「真摯に日々取り組んでいる研究者は、誰かがしっかりと見ている」という言葉は、流されてもその先でベストを尽くせば、良い結末を招くという考えと共に、以降の研究に於いても私の心の支えになりました。
数多くの博士を輩出した熊井先生が指導でこだわっていることはありますか。
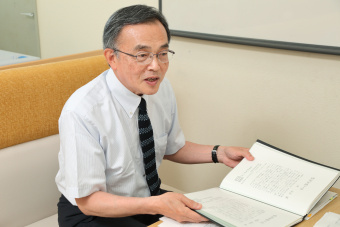
学生の特性を理解し、その天分を最大限に活かせるよう支援されて来られた締めくくりとして、卒業する学生全員に、個別に研究室修了証を授与しています。各人の個性を記述するため、すべて内容が異ります。先生はその写しをファイリングして大切に保存されておられます。
私は自分でテーマを選び取り、それを追いかけることで新しい知見を獲得するのが、博士人材の最大の特徴だと思います。ですから私の研究室では、入ってきた博士課程の学生に、事細かく研究内容を指示することはありません。いくつかのテーマの幅を広めに用意し、その周辺で個人のテーマを決めてもらい、時折サジェスチョンを行うことで軌道修正をしてもらうといった進め方です。幸運なことに私のこれまでの研究テーマをリスペクトして入ってくれる学生ばかりなので、こちらの意向と乖離することはまずありません。
それに私は学生と一緒に研究室を育てるという方針で運営しています。学生たちは中学生時代に国語と英語が好きで理数系が得意ではなかった私よりも、理系的なセンスを持っています。私が研究の進行でボトルネックに差し掛かりブツブツと問題解決をどうしようかと自問自答していると、それを耳にした学生が翌日に「こうしてみました」という解決案を持ってくることもあります。
そうして学生たちの自発性を尊重し、共創していく雰囲気のある研究室から卒業する博士をはじめ、学生全員に私は研究室修了証を授けています。そこに書かれている内容は、一人ひとり異なります。どんなことをやって、どんな失敗をして、どんな成果を残したのか、周囲にメールを送ってエピソードを集めて書き上げます。新たな門出を応援していきたいという想いがそこにあるのです。
熊井研究室からどのような博士人材が巣立って行かれましたか。
産業界との共同研究を絶え間なく行ってきた私の研究室には、博士の学位を取得後に企業への就職を希望する学生が多く、実際に今は多数の卒業生がIHIや旭化成、日産自動車、UACJ、日本軽金属、神戸製鋼所、リョービといった著名企業で研究や開発の要職に就いています。私が学会で会長や副会長を務めた際に、企業側から卒業生が代表として参加することも多くなってきました。実はアカデミアに残るよりも、産業界で活躍したいと考える学生の方が多いのが、私の研究室の特徴です。それでも、アカデミアを進路に選んで研究成果を上げている卒業生も少なくありません。そのまま東京科学大学に残る他、日本大学、東京電機大学、群馬高専、韓国の大学などでも卒業生たちが研究者として活躍しています。
博士・ポスドクへの応援メッセージをお願いします。

産業界との共同研究が盛んであり、多くの学生が研究室から博士号取得後に企業へ就職しています。企業に就職しても、新たな視点で果敢に挑戦を続けて欲しいと、考えておられます。
修士課程を経て博士後期課程に進学後に自ら研究テーマを設定し、その研究を進めていく中で真理を極め、論文にまとめ上げることではじめて博士の学位取得の条件が整います。そして、このプロセスを通して博士の学位を取得した皆さんには、どのようなテーマにも柔軟に挑んでいけるフレキシビリティが備わっているはずです。それゆえ、企業の研究部門や公的な研究機関にステージを移しても、今までのセオリーや手法を踏襲するだけの硬直化した研究姿勢ではなく、新たな視点に立って果敢な挑戦を続けて欲しいと思います。そこには間断なく努力する必要があるでしょうし、成果のなかなか見えない不安を伴うかもしれません。でも、真摯に取り組む姿勢があれば、必ず誰かが見守ってくれています。必要な時になれば、きっと手を差し伸べてくれるでしょう。そして一つの到達点を迎えた時、次にまた新たなテーマが目の前に現れることでしょう。

