博士の先達に聞く
博士人材に向けて、未来社会を見据えた従来と一線を画す研究哲学を訴求する九州大学片山教授。
-

-

日本の産業界の国際競争力の低下が喧伝されるようになって久しい昨今、数ある要因の一つに産業界において博士人材の実力が十分に発揮されていないことが挙げられます。イノベーティブなテクノロジーやそれによるビジネスモデルを生み出し、産業界の発展の原動力となる博士人材の絶対数が、産業規模の割に諸外国と比べると少ないことも指摘されています。また、産業界が国内の博士人材を活かしきれていないという側面もあるようです。
こうした将来の国力に関わる重要問題を深刻に受け止めている政府は、様々な施策を打っています。一例として文部科学省は、大学院教育改革の推進や博士後期課程学生への経済的支援、さらにキャリアパスの多様化推進に向けて「博士人材活用プラン〜博士をとろう〜」を取りまとめて公表。2040年における人口100万人当たりの博士号取得者数を、世界トップレベルに引き上げることを新たな目標として掲げました。一方のアカデミア側も、博士後期課程に進学する学生への様々なサポートを強めています。
しかし、このような国内における博士人材を育成する環境の整備だけでは、国力を増大させるという肝心の成果は期待出来ないと憂慮なさっているのが、九州大学工学研究院の片山教授です。
片山先生は、アカデミアも産業界も、研究に向かう姿勢や求める成果が経済発展を続ける先進諸国とは大きく乖離していると語ります。そして、博士は未来社会の価値観にどのように向かっていくべきか、を自らの研究と数々の産学連携のコラボレーションで示されています。そこで片山先生の現在の研究内容とその背景にある強い想い、博士人材のあるべき姿などを、これからの日本を担う博士人材や産業界に向けて熱く語って頂きました。
※本文内に挿入している画像は、クリックすると拡大されます。
(掲載開始日:2025年1月24日)
片山先生の考える日本の研究の本質的な問題点についてご教示下さい。

日本の学術研究や技術開発は、特定の技術領域に閉じこもりがちで、新しいマーケットを創出することが難しい傾向にあります。特に、AIの導入目的が業務効率化に留まっている日本に対して、欧米諸国は未来を見据えた研究開発にまで応用している実状を片山先生は指摘されています。
私が現在取り組んでいる研究分野は、バイオメディカルエンジニアリングと呼ばれる、一義的にはヘルスケア分野で未解決な問題について化学をベースとしたテクノロジーで解決しようとする領域です。そこでは治療技術や診断技術の進化から創薬まで幅広く視野に収め、化合物合成や細胞の改変、動物実験、遺伝子組み換えまで必要であればすべて取り組みます。医療のための化学であればすべて研究対象とすることから、「医用化学」を名乗っています。そして、こうした従来の学術領域における垣根を乗り超えていく私たちの姿勢は、日本のアカデミアや産業界が抱える最も重要な課題の解決策とオーバーラップしているのです。
近代以降、日本の学術研究や技術開発は、自らの属するカテゴリーの中で研鑽を続けてきました。例えばバイオメディカルエンジニアリングとしばしば同義的に扱われる言葉に「医工」があります。これは、機械や電気電子、情報といった工学部系の技術を現実の医療問題に適用することで医療の発展に寄与しようとする技術分野として定義されていますが、現実は広範囲を俯瞰した視点から研究が進められているわけではありません。研究開発の起点は往々にして個々の研究者が立脚する一定の技術領域からはみ出すことはなく、予測可能な技術の到達点以上には成果が広がらないのです。
医工に限らず国内の様々な学術領域が、このような一方向の進化・発展スタイルを近代以降相変わらずに踏襲してきました。マーケティングの観点から言えば、リスクを恐れ、上手くいく確率の高い研究や開発のみに手を出してきたと言えるでしょう。それではまったく新しいマーケットを創出することは出来ず、既存のマーケットの奪い合いにしかなりません。
実際に、10数年前から日本のこうした研究姿勢や開発姿勢は世界的に通用しなくなってきました。現実問題として社会の大きな変化を主導しているのは、新しい価値観を創造する米国を中心とした欧米各国のアカデミア並びに産業界であり、日本は追従せざるを得ない状況が続いています。例えば、これから社会を大きく変えると言われる AIですが、日本のAI導入目的のほとんどが業務の効率化となっています。他方、先駆的な海外企業はAIを今までは出来なかったビジネスに使おうとします。発想が最初から異なっています。海外企業は現在の延長上にはない未来の具体的なイメージを描いて研究や開発に投資を行っているのです。今後の10数年はさらに社会の構造や価値観が大きく様変わりするはずです。このままでは日本の大学や企業のプレゼンスはいっそう低下するのではないでしょうか。
逆に言えば、国際社会を先導する国々ではどのような研究開発が行われているのか。あるいは世界を牽引するようなイノベーションはどのようにすれば生み出せるのか。それは一つの学術領域の枠内で思索をめぐらしたり、試行錯誤を重ねることではないのは間違いありません。この先テクノロジーが進化すれば世の中にどのような価値観とそれを投影した社会構造が到来するか、そうした世界の最先端の未来像を洞察していくフィロソフィーや気概を持った人材こそが先頭に立てるのだと考えています。そして、そうした社会を変える駆動力となるのは、クリエイティビティを持つ博士人材であることは言うまでもありません。
片山先生はこの先の世界はどのように変わっていくと想像されますか。
未来の社会構造や価値観がどのように変化していくのか、様々な方向性が考えられますが、最も大きな役割を果たすのはAIやビッグデータ解析を実装してどんどん進化し続けるネットワークでしょう。これまでの教育は、知識という情報を与える行為でした。知識を蓄えた人に社会的価値があると考えられていたからです。ところが現在では、必要な知識のほとんどがネットワークから得ることが出来ます。さらにその知識をベースに正解は何かという判断も、ネットワークが出してくれるようになってきました。専門人材を通さずに最適な出会いを創出するマッチングアプリなどは典型的な例だと言えます。何事においても意思決定を個人ではなくネットワークが行う時代が、すでに到来しつつあるのです。
そうした時代が定着する前に、日本は意思決定に最も深く関与するネットワークを持っていないと、海外のネットワークに膨大なデータをどんどん吸い取られるだけで、支配される状況になってしまいます。利益を吸い上げられるだけの国に成り下がってしまうのです。
片山先生が取り組まれている新たな研究アプローチ例をご紹介下さい。
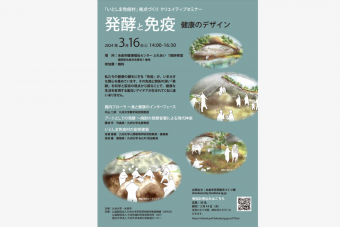
「いとしま免疫村」で開催されるセミナーの告知ポスター。九州大学の医学、工学、芸術工学、人間環境学などの専門分野と糸島市の産学連携のワークショップにて、「免疫」をテーマに先端的な科学やテクノロジーを元に新しい共創文化を発信しています。
以上のような懸念や憂慮を払拭すべく、九州大学では、未来の人類の意思決定に深く関与する強力なネットワークを構築し、社会の新たな価値観を主導して行こうとしています。それが新しい医療ネットワークです。人は幸せでありたいし、そのためには健康であることが大前提です。そこに大きく寄与するネットワークを日本が構築することが出来れば、世界中の人々が信頼を置き、周辺産業は活性化し、国際マーケットでの主導権を握ることが可能になります。
この医療ネットワークは顕在化している医療のエビデンスを公開するだけのものではなく、未知のエビデンスを探索するデータ駆動型のシステムです。仮説を立てて予測数値をデータで証明するのではなく、予想さえもしなかったエビデンスに相当するものをビッグデータから抽出し、それに従って意思決定をしていくシステムになります。
例えば私がプロジェクトリーダーを務めるオープンサイエンスプラットフォーム構想は、九州大学医学部教授の中島先生が主導して九州大学病院が提供する30万人分の電子カルテデータ、同じく医学研究院准教授の福田先生が主導するプロジェクトが提供する自治体180万人分の医療レセプトデータ、福岡市に本社を置き九州を中心に全国で200以上のスーパーマーケットを展開する株式会社トライアルホールディングスが提供する200数十万人分の顧客購買データ、その他水質検査データや大気環境測定データ等のオープンデータを個人情報を消去した形でビッグデータ解析することにより、医学的仮説なしにデータ駆動型に免疫疾患因子を探索します。特に現在、九大病院の患者データと顧客購買データの突合も開始して生活習慣と健康上のリスクの解析に進めようとしています。そうすることで予想外の因子をエビデンスベースで探索することができ、そこから予想外の価値の発想が可能となります。ここでは、本学のみならず広範な分野の企業が会員となり価値の共創を進めています。
また、これと併行して九州大学に近接する糸島市と協力して、「免疫」をテーマとした対話と共創の場である「いとしま免疫村」を糸島市の主導で設立しております。この構想が実現しようとしているのは糸島市民の免疫系疾患の検出・治療に役立てる医療行為だけではありません。免疫をテーマに商品やサービスの開発を行い、レストランやクッキングスクールやアートイベントを創出していきます。データが明らかにした免疫に関するエビデンスで理想の健康社会をデザインし、市民を含むあらゆるステークホルダーが「楽しく」集い、健康について「創造的に」なれる場所を築こうとしているのです。さらに、上記で見つけた因子や、創出されたアイデアの実証や介入、市民と直接データで繋がるエンゲージメントネットワークの構築にも取り組もうとしています。
これらの取り組みは、医療DXを推進するプロジェクトであり、臨床情報、遺伝情報、環境・生活習慣情報を統合解析し、学習する医療サービス「ラーニングヘルスシステム(LHS)」で継続的に改善サイクルを回すことにより、予防医療への貢献やWell-Beingの実現を目指します。また、将来的には医学や科学の進化・発展に繋げることを視野に入れています。
片山先生が博士人材として産業界からアカデミアに戻られた経緯を教えて下さい。
私は九州大学で合成化学の一領域である分析化学を専攻し、博士課程を修了後、大学の教授が立ち上げた工業分析用試薬等を作る会社に就職しました。そして産業用試薬の開発にしばらく従事しました。その後、その企業がバイオ試薬の開発に着手することになり、私も責任者の一人になり、独学で専門領域外であった生命科学を学んで種々の製品を世に出すことができました。プロジェクトも安定したこともあり、私はその企業の中で36歳にして、やれることをやり切ったという想いがありました。
そんな時に、母校から戻ってこないかという声がかかったのです。私はバイオ試薬の開発から専門領域を一挙に広げ、ライフサイエンス全般に波及する研究に関われるチャンスだと捉えました。しかも当時は私がやりたいと考えていた化学の分野で細胞や動物を使う研究は皆無であり、そうした新しい研究が大学で出来ることに、途方も無い楽しさを予感したのです。それで私は企業での安定したポジションを放棄し、アカデミアに場所を移しました。まさに、私自身、自由に新しい価値観を求めることができると考えたからです。
博士・ポスドクへの応援メッセージをお願いします。
これまで述べてきたように、これからの博士は今の狭い専門性にこだわることなく、未来社会における価値や解決課題を思い描き、そこからバックキャスティング* で進める研究アプローチが求められます。博士は未来をデザインしていくフィロソファー(哲学者)であらねばならないのです。そうしなければ、新しい価値はつくれません。同じことは産業界や国家にも言えます。
少なくとも博士人材には、今までのように専門分野の知識を一つずつ蓄積していく知識人を目指すのではなく、変化の激しい未来を予見し、必要に応じて専門分野・領域の枠を大胆に踏み出していくマインドが必要になります。今まで習得してきた専門性を離れ、新しい世界に飛び込むのは勇気や大胆さが要ることでしょう。しかし、その変化していく状況を楽しめることができたら、一大変化を生み出せる存在になれるのではないでしょうか。
* 目標とする未来像を描いてから、その未来像を実現するための道程を未来から現在へと時間の流れに逆行して設計する手法。


