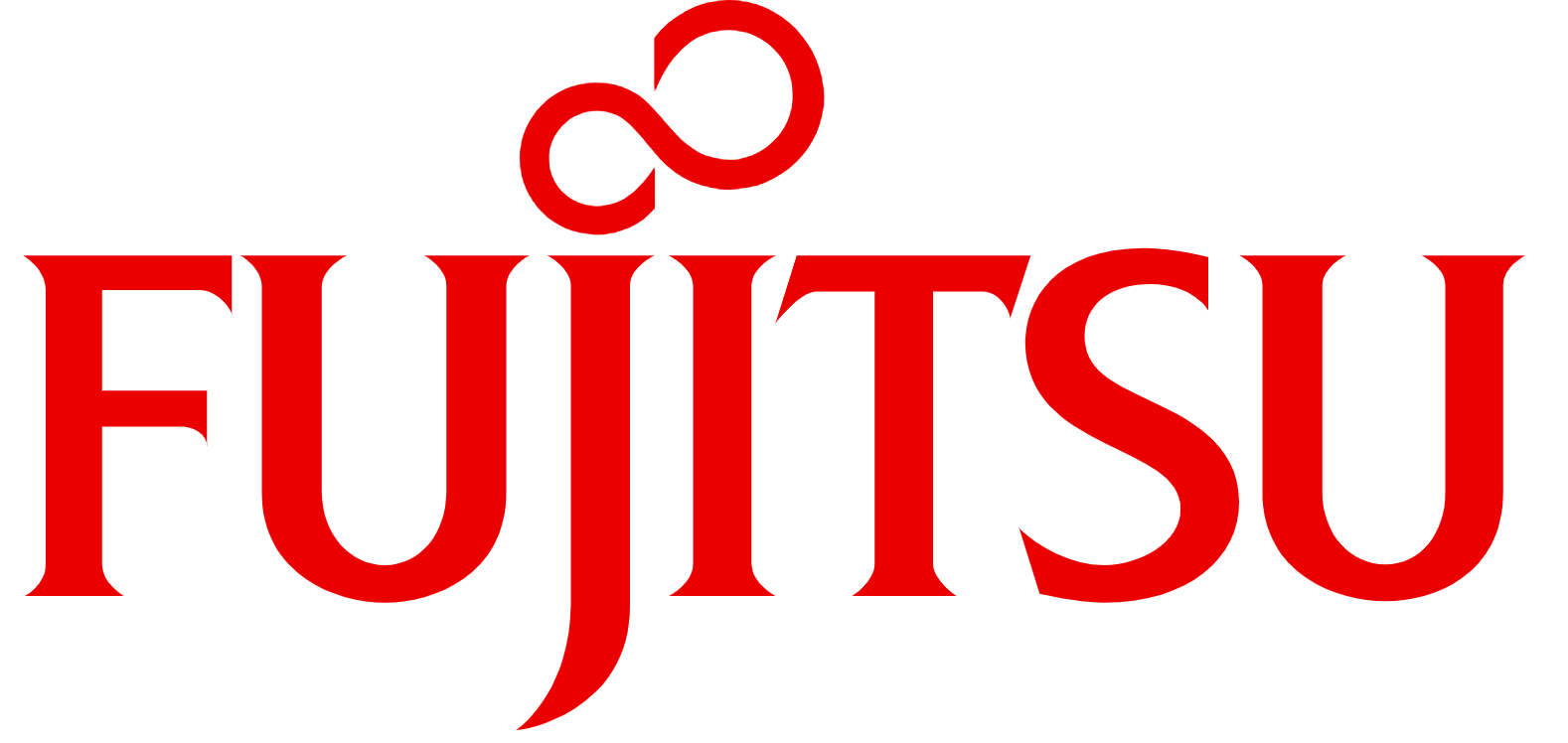産業界で活躍する博士インタビュー
社内の研究員や修士学生の博士号取得支援等、 様々な博士人材活用施策でイノベーションを喚起する富士通。
多様なITソリューション、先端通信ハードウェア、最新電子デバイス等を提供する総合ベンダーの富士通株式会社。その広範囲かつグローバルに展開する大規模な事業スケールに加え、理化学研究所と共同開発したスーパーコンピュータの「富岳」のローンチ直後の処理能力が世界ランキングで首位に立ったことや世界最高レベルのAI技術、量子コンピュータに象徴されるように、様々な技術領域で多くのイノベーティブな実績を残しているTechnology Companyとして知られる存在です。
その富士通は、研究員を大学院博士課程へ派遣し、博士号の取得を支援する仕組みである「博士号取得支援制度」をはじめ、以前から博士人材の活躍に向けた取り組みに力を入れてきました。社内の博士人材を重要度の高い研究に積極登用するのはもちろん、アカデミアと共創する先端研究にも多くの博士人材を送り込んでいます。
今回は富士通において博士人材の活躍の先駆的な取り組みを担うR&D人事部シニアマネージャーの輿秀和氏に、同社が期待する博士の人材像やその卓越した研究力を引き出す各種制度や風土を、そして奈良女子大学大学院博士課程を経て富士通に入社された石川千里氏に、博士人材がその価値を存分に発揮している同社の就業環境についてお話を伺いました。
取材地:Fujitsu Uvance Kawasaki Tower
※本文内に挿入している画像はクリックすると拡大されます
(掲載開始日:2025年 7月 31日)
富士通は博士人材のどのような価値を評価していらっしゃいますか。

博士人材は社会課題の解決に貢献する良い問いを設定し、それを解決していく力を持っています。
現在国内では約440名の博士人材が活躍しています。
富士通では博士人材について、一つ以上のテーマを極めて得た価値の高い専門性と共に、別の専門領域でも活かすことができる汎用的なスキル、そして、一つのことに熱中する力などを評価しています。最も期待する能力は、社会課題を解決する可能性を持った研究テーマを自ら設定し、追究していく力です。当社は、ITやデバイス開発技術をベースに、イノベーティブな製品やサービスを提供するTechnology Companyですが、未来の世の中が必要とする技術を見定め、社会実装していく研究開発の起点の役目を果たす研究員の多くが博士の学位を取得しています。社会の最前線における重要な技術課題は刻々と変化していきます。博士人材にはそうした変化を察知し、研究に落とし込んでいく能力が備わっていると考えています。
実際に、国内では約440名の博士人材が活躍しており、グローバルに目を向ければ世界8ヶ国に展開している富士通研究所に所属する研究員の35%以上が博士号取得者となっています。また、博士人材の配属先は富士通研究所など主にR&D領域を担う部門となっていますが、ジョブ型人材マネジメントを2020年から導入し、コンサルティングを行う部門やクライアントへの技術提案を起点に協業を進めていく「オファリングビジネス」を担う部門などにも博士人材の活躍ステージが広がっています。
富士通の博士人材に対するキャリア支援の姿勢をご紹介下さい。
富士通は、Technology Companyとしてイノベーションの創出に貢献できる高度な専門性や汎用的な力を持つ博士人材を重要視してきました。長年適正な報酬で通年採用してきただけでなく、育成や活躍支援にも力を入れてきました。
例えば、研究員の中から毎年7名程度を選抜し、富士通に在籍しながら大学院博士課程に派遣して博士の学位取得を支援する「博士号取得支援制度」を、1998年に開始しています。試験料・入学金・授業料等を会社が全額補助するこの制度で、これまでに189名の利用実績があります。この制度は単に学位取得を支援することのみが目的ではなく、研究員の専門性を高めると共にグローバルな研究者としての自律的なキャリア形成を支援する仕組みとなっています。さらに、富士通とアカデミアとのリレーション強化も見込まれています。
博士の学位取得を目指す学生への支援も以前から産学連携で進めてきました。修士課程修了予定の学生の進学・研究支援や、現在博士課程で研究を進める学生への研究・キャリア支援などです。そうした幾つかの産学連携の人材育成施策の一つに、「招聘研究員制度」があります。この制度は修士課程・博士課程の現役学生と有期契約社員の雇用契約を締結して長期有償インターンシップを実施するもので、学生にも研究者としての自負をもって企業の研究に本格的に取り組んでもらいたいという想いが込められています。
他にも富士通の研究員が国内外の大学に常駐・長期滞在し、さまざまな分野の専門人材や学生たちと研究活動をする産学連携の取り組みである「富士通スモールリサーチラボ」があります。現時点では国内13校、海外4校に展開しています。異分野融合による社会課題の解決や効果的な共同研究、人材育成を行っています。
中でも富士通の特徴的な取り組みをご紹介下さい。

卓越社会人博士制度は、大学と富士通が手を組みイノベーションを引き起こす博士人材の育成を目指すと共に、博士課程修了者数が伸び悩み日本の研究開発力が低下するのを食い止めようという新しい就職・雇用の取り組みです。富士通が日本で初めて制度化しました。
2021年、修士課程から博士課程に進学する学生を富士通が正社員として採用し、基本給や賞与等を支給しながら博士課程の研究と富士通の業務としての研究に同時に取り組む「卓越社会人博士制度」をスタートしました。
アカデミックな先端研究を進める大学と社会課題の解決に結びつく研究を進める企業が一体となって、日本の将来を背負って立つ優秀な人材を継続的に輩出する取り組みであり、現在は九州大学、東京大学、東京科学大学、大阪大学など、10校まで展開しています。この制度を利用する学生は大学院で最先端の研究に深く触れ、富士通では企業研究員の立場で社会実装を見据えた研究に同時に従事することになります。
今後の博士人材の採用についてどのような構想をお持ちでしょうか。

社会の現場を知る企業の人間が、大学でキャリア教育を行う意義を感じ、輿さんは北海道大学でセミナーを開いてきましたが、大学や学生からのニーズに応え、2025年度より大学院共通科目の授業となり、輿さんが講師として参加します。
2023年度から北海道大学と富士通人事が共創教育を進めています。大学でのキャリア教育に企業人が深く関わっても良いのではないだろうかという想いからスタートし文理を問わず、さらに富士通に限らず広く産業界での就業を目指す大学院生を対象に、企業で活躍していくための力を事前に養うことを主眼に置いています。2023年度は単発のキャリアセミナーの開催でしたが、2024年度には全4回の共創教育キャリアセミナー開催に拡大し、2025年は大学院共通科目の通年授業に発展しています。
以上のように、富士通はTechnology Companyとして、博士人材の増加と彼らがその実力を存分に発揮し、その活躍の場を広げる数々の施策を長年実施してきました。その取り組み成果が続々と形になり始めた昨今、富士通における博士人材は、今後ますます複雑化する社会課題の解決に貢献するイノベーションの創出や技術革新をリードする存在として全社を牽引していくと考えられています。
石川様の大学院時代の研究内容と富士通入社を選択した理由をお話し下さい。
私は奈良女子大学の理学部に入学し、大学院博士後期課程まで修了しました。専攻したのは情報科学であり、研究テーマはコンピュータを使った信号解析です。具体的に言えば、地震の直前に地中で岩石が破壊される際に流れる微弱な電流を、電車から地面に流される、より大きな電流などをノイズとして取り除いて捉え、地震の直前予知に繋げるという内容です。地下電流を計測するようなフィールドワークは行わず、データ自体は他の研究室の教授から頂き、データを解析して可視化する仕組みづくりに注力していました。解析ソフトウェアは後輩と共に自らプログラミングを行って制作しました。
そんな私がアカデミアに残らず富士通への就職を選択したのは、可視化ソフトをつくることでものづくりの楽しさを再確認したからです。もともと手芸やDIY工作が趣味でした。それで基礎的な研究を続けるよりも、実際に他者に使って喜んでもらったりする製品やサービスの研究開発に挑みたいと考えたのです。そうして入社後、私が配属されたのは音声解析のグループ。担当したのは、高齢者が携帯電話を使用した際に聞き取りやすい音がどのような信号であるか、波形から最適解を検証していく業務でした。大学での電流解析とは波形解析の面で通底する部分が多く、テーマ的に連続していたと思います。
石川様の現在の研究テーマとそこに至る経緯を教えて下さい。
入社から数年が経過したのち、1年間の産休育休を取得しました。復帰後に配属されたのはAIを用いた映像解析で人間の行動分析を行う技術を研究するグループでした。工場内等で人の動きを検出して安全性を担保しながら作業工数の削減に役立つ技術です。以前の研究テーマとは大きく異なる上、AIに関しては触れたことが殆どなかったこともあり、復帰当初は若干の当惑がありました。就労時間外は子育てに追われることからじっくりとAIに取り組む時間もありません。
しかし、上司とは以前から面識があり、同僚からのサポートも手厚かったことで疎外感などは全くなく、社内の教育システムを利用しつつ、周辺論文を効率よく読み込むことでAIに関する理解が一気に進みました。Pythonのプログラミングが不可欠なのですが、大学時代からの研究でC++のプログラミングスキルを取得していたことも役立っています。元々、新しい研究テーマに遭遇した際の対処は幾度か経験してきたので、壁を乗り越えるノウハウや基礎スキルを持っていたのです。
最近では、AIの研究としてLLMに力を入れ始めています。具体的な例はまだ言えないのですが、私の所属する部署では、LLMを様々な領域の現場で活用していく、活用するための課題を抽出し、技術的な障壁を新しい技術で解消していくという活動を行っていきます。最先端の技術をより効果的に現場で活用していく、という点で、携帯電話向けの技術や行動分析AI技術の研究の時と一貫しています。
富士通には博士人材が研究を行う上で、どのような魅力がありますか。

企業のニーズ、世の中のニーズ、近未来のニーズが我々の研究のテーマとなります。スケールの大きさだけでなく、変わったテーマの研究も数多くあり、様々な課題に取り組むことが出来ることが富士通の研究環境です。
JR川崎駅直結の Fujitsu Uvance Kawasaki Tower 内の社員食堂で。
富士通社内で博士人材はとても重宝されていると感じています。重要な研究テーマにアサインされるだけではなく、その際に自らの意見は十分に尊重されます。また、上層部からは管理職に昇格させたいという雰囲気も伝わってきます。社内には先端研究とマネジメントを両立させている博士人材の先輩が数多く活躍しており、研究職と管理職の両立は不可能ではありません。
しかし、私はまだまだ研究に軸足を置きたいと考えています。同じ研究グループ内の仲間たちと協力し合いながら進めている研究によって、大きな成果を引き寄せる期待があります。実は私は単純ミスを起こしてしまうことがありますが、そんな粗忽な面を持つ私を時に助けてくれたり、時に頼ってくれたりする仲間の存在は大きくありがたいですね。
各企業の研究グループには、近未来の世の中のシーズが降りてきます。社会に直結した研究がしたかったら、産業界に進むことをお勧めします。その中でも富士通の特徴は共同研究を行う大学が多彩で、協業相手も大手の有名企業がほとんどであることです。そこではスケールの大きなテーマや一風変わったテーマの追究が行われているなど、多様な研究対象が博士人材を待っています。また、プロジェクトごとに研究テーマは変わりますから、次々とテーマを変えて新たな課題に挑みたいと考える方も、富士通を研究拠点として選ぶと満足されるのではないでしょうか。